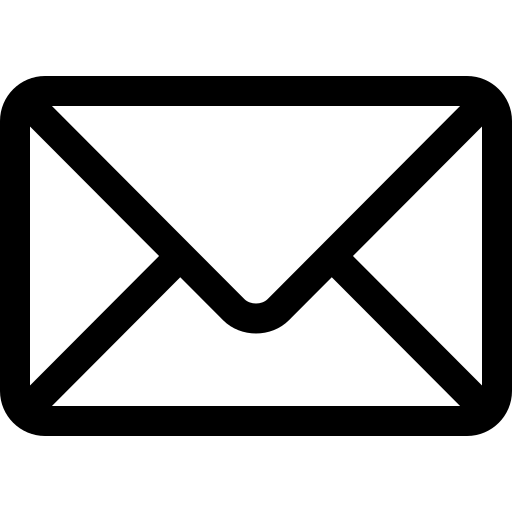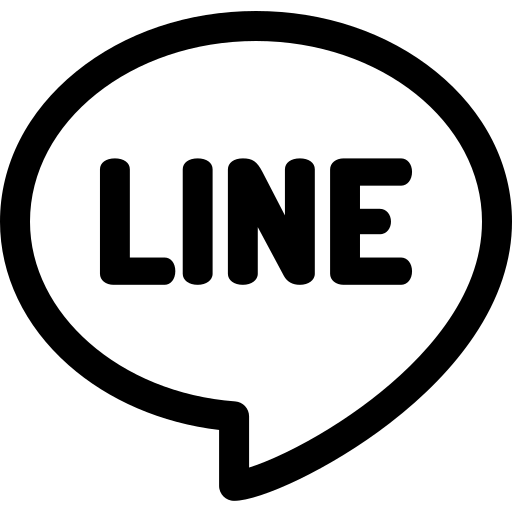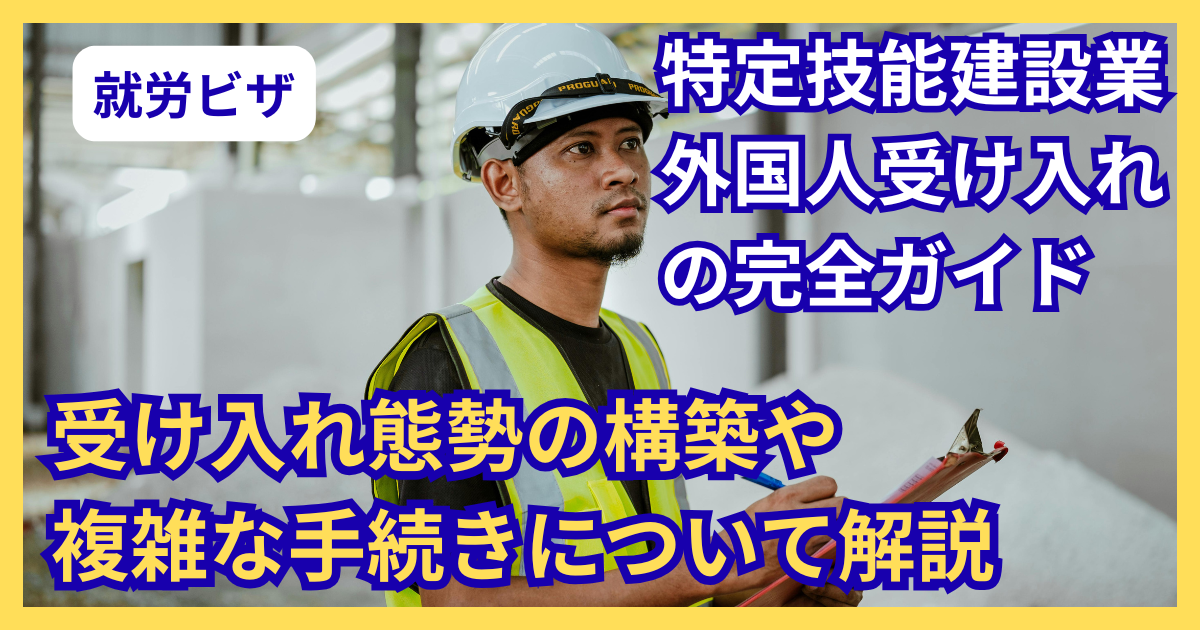特定技能「建設業」での外国人受け入れ完全ガイド
〜協会加入・受入計画・キャリアアップ登録・支援体制まで〜
近年、建設業界では深刻な人手不足が続いており、即戦力となる外国人材の受け入れが進んでいます。その中でも注目されているのが「特定技能」制度です。
しかし、建設分野で外国人を雇用する場合、他の業種にはない協会加入や受入計画の認定、キャリアアップシステムへの登録といった独自の手続きが求められます。
さらに、外国人を雇用した後は、登録支援機関との連携または自社での支援体制構築も義務付けられており、適正な受け入れ管理が不可欠です。
本記事では、建設分野の特定技能制度の概要から、実際の受け入れまでの流れ、注意点までを行政書士の視点で詳しく解説します。
特定技能制度とは?
特定技能とは、一定の技能と日本語能力を有する外国人が日本国内で就労できる在留資格で、2019年4月に新設されました。
人手不足が特に深刻な14分野(介護、外食、宿泊、建設など)で活用されています。
建設業では、外国人が技能実習で培った経験を活かし、より高度な技能を発揮できるように設計された制度です。
特定技能には以下の2種類があります。
- 特定技能1号:一定の技能を持つ外国人(在留最長5年)
- 特定技能2号:熟練技能者(在留期間の上限なし・家族帯同可)
建設分野では、特定技能1号・2号のいずれも対象となります。
建設分野での対象職種
建設業の特定技能は、他業種よりも細かく職種が設定されています。主な対象は以下の通りです。
- 土木工事
- 建築工事
- 電気通信工事
- 塗装工事
- 鋼構造物工事
- 建設機械施工
- 内装仕上げ工事 など
これらの分野で技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能として就労可能になります。
技能実習から特定技能への移行が主流
建設業では、技能実習2号修了者が特定技能1号に移行するケースが大多数を占めています。
移行者は試験が免除されるため、企業としてもスムーズに雇用を継続できます。
ただし、技能実習で従事していた職種と特定技能の職種が同一分野内であることが条件です。
分野が異なる場合には、新たに技能試験と日本語試験を受験する必要があります。
建設分野では協会への事前加入が必須
建設業で特定技能外国人を受け入れる場合、他分野と大きく異なる重要な要件があります。
それは、国土交通省が指定する「建設特定技能受入協議会」への加入です。
▶ 協議会加入の目的
建設業は現場が多岐にわたり、元請・下請関係も複雑です。そのため、外国人労働者の適正な受け入れと雇用管理を行うために、協議会が一元的に情報を管理しています。
協議会への加入によって、
- 不正就労・不適正受け入れの防止
- 外国人の安全教育・技能向上支援
- 業界全体の透明性確保
といった役割を担うことになります。
加入しない企業は、特定技能外国人を受け入れることはできません。
「受入計画書」の認定を受ける必要あり
建設分野では、協議会加入後に「受入計画書」を作成し、国土交通省の認定を受けなければなりません。
受入計画書には、外国人が従事する業務や教育体制、労働条件、キャリア形成支援などが詳細に記載されます。
▶ 主な記載事項
- 外国人の職務内容・配置先
- 賃金や勤務時間などの労働条件
- 指導員体制・安全衛生管理
- 日本語教育・キャリアアップ支援
- 生活支援・相談体制
認定を受けていない企業は、特定技能外国人を雇用することができません。
また、受け入れ後も計画通りに運用されているか、定期的に報告・監査を受けることになります。
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録も義務
建設分野の特定技能では、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録が義務付けられています。
▶ CCUSとは
CCUSは、建設業に従事するすべての技能者の就業履歴・資格・現場経験などをデータベース化し、技能を「見える化」する国のシステムです。
特定技能外国人本人と雇用する企業の双方が登録する必要があります。
登録することで、
- 技能・経験の証明が容易になる
- 賃金設定の透明性が確保される
- 企業のコンプライアンス強化につながる
といったメリットがあります。
未登録のまま就労させると、受入計画違反と見なされる可能性があるため注意が必要です。
登録支援機関との連携、または自社支援体制の構築が必要
特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安心して働けるよう、支援計画を実施しなければなりません。
これは建設業に限らず、すべての特定技能分野に共通する義務です。
▶ 支援業務の主な内容
- 生活オリエンテーション(日本のルールや生活マナーの説明)
- 住居の確保や生活に必要な契約支援(銀行口座、携帯など)
- 日本語学習の支援
- 日常生活・職場での相談対応
- 転職・帰国時の手続き支援
- 行政手続きのサポート(市役所・健康保険など)
これらを自社で体制を整えて実施するか、または登録支援機関に委託することが求められます。
▶ 登録支援機関に委託する場合
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された専門機関で、外国人支援の経験や体制を有しています。
中小企業では、専門知識や人員不足から自社対応が難しいケースも多く、登録支援機関に委託するのが一般的です。
ただし、委託しても最終的な責任は受け入れ企業にあります。
▶ 自社で支援体制を構築する場合
大手建設会社などでは、外国人担当部署を設けて自社で支援業務を行うケースもあります。
自社で行う場合には、支援担当者の配置、日本語対応体制、緊急連絡網の整備などが必要です。
支援計画が適切に実施されていないと判断された場合、特定技能の受け入れ停止処分を受けることもあります。
受け入れの全体的な流れ
- 協議会への加入
- 受入計画書の作成・認定
- キャリアアップシステムへの登録
- 登録支援機関との契約(または自社支援体制構築)
- 在留資格認定証明書交付申請(入管手続き)
- 外国人の入国・雇用開始
- 定期報告・教育・生活支援の継続実施
建設分野は入管だけでなく、国土交通省や協議会など複数機関の管理下にあるため、手続きが煩雑です。
行政書士など専門家のサポートを受けながら進めることで、スムーズな受け入れが可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 登録支援機関に委託すればすべて任せられる?
A. 支援業務の多くを委託できますが、最終的な責任は雇用企業にあります。契約内容を明確にし、定期的な報告を受けることが重要です。
Q2. 協議会への加入費や年会費はかかる?
A. はい。受け入れ人数や企業規模によって異なりますが、初期費用・年会費が必要です。
Q3. 受入計画の認定期間は?
A. 審査には通常1〜2か月ほどかかります。外国人の雇用時期から逆算して早めに準備しましょう。
行政書士によるサポートの重要性
建設業の特定技能受け入れは、一般の在留資格手続きよりも複雑です。
協議会・国交省・入管・登録支援機関の手続きをすべて理解して進めるには、専門的な知識が不可欠です。
行政書士に依頼することで、
- 協議会加入申請
- 受入計画書の作成・認定申請
- 登録支援機関との契約書作成
- 入管申請書類の作成・提出代行
などをトータルでサポートできます。
まとめ|適正な体制で安心の外国人受け入れを
建設業の特定技能制度を活用するには、
・協会(協議会)への加入
・受入計画書の認定
・キャリアアップシステム登録
・登録支援機関との連携または自社支援体制の構築
という4つの柱が欠かせません。
これらを適切に整備することで、外国人材が安心して働ける環境を整え、企業の信頼性と持続的な人材確保につながります。
制度の理解や手続きに不安がある場合は、経験豊富な行政書士にご相談ください。
最新の制度情報をもとに、スムーズな受け入れをサポートいたします。
就労ビザのことでお悩みの方へ
特定技能ビザの取得や外国人材の受け入れ態勢の構築について、詳しく知りたい方はぜひ当事務所にご相談ください。
経験豊富な行政書士が、申請手続きや書類準備まで丁寧にサポートいたします。ひまわり行政書士事務所では、おひとりおひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを行っています。
「こんな場合はどうすればいい?」
そんな疑問もお気軽にご相談ください。
事務所概要
事務所名:ひまわり行政書士事務所
所在地:〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」5番出口から徒歩1分
代表:金井 優美
営業時間:平日 10:00〜18:00
TEL:06-7878-5359
Email:info@himawari-office.info